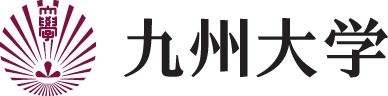「組織」対「組織」の産学官連携
○共同研究部門
共同研究部門は、九州大学と民間企業等との組織的かつ中長期的な組織対応型連携の研究事業の枠組みにより、民間企業等からの共同研究費で学内に共同研究に係る拠点(共同研究部門)を設置し、特定の研究分野について一定期間継続的に共同研究を実施します。
当該共同研究部門の運営及び教育研究業務に従事する「共同研究部門教員」を雇用・配置し、共同研究を実施します。
運営方針・計画
管理運営・評価
大規模事業
財務
教育
研究
図書館
情報サービス
産学連携
知的財産
社会連携
男女共同参画
服務・倫理等
勤務時間・休暇等
教員の業績評価
給与・福利厚生等
安全衛生
経理事務
施設・設備利用
その他(資料集)
共同研究部門は、九州大学と民間企業等との組織的かつ中長期的な組織対応型連携の研究事業の枠組みにより、民間企業等からの共同研究費で学内に共同研究に係る拠点(共同研究部門)を設置し、特定の研究分野について一定期間継続的に共同研究を実施します。
当該共同研究部門の運営及び教育研究業務に従事する「共同研究部門教員」を雇用・配置し、共同研究を実施します。